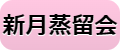実際に「夏だ~!」と感じるよりもずっとまえに、自然も体も、夏へと移行を始めています。
今から、夏の養生を始めておくとこの後がずっと楽です。
夏は心に負担がかかる。
夏には「心」(しん)の働きが活性化します、季節の中で一番「陽」が強い夏は、体の中で最も陽が強い「心」の働きが強まるからです。
東洋医学的「心」は、西洋医学的な心臓の機能だけでなくて、精神活動もつかさどります。人体の働きや機能をふくんでいます、以下。
・血液循環 心臓、血管系
・精神活動
・睡眠
「心」が変調すると、熱っぽくイライラしたり、睡眠障害などの症状が現れます。
余分な熱を取り去り、うるおいを増してくれる食材をとりましょう。
夏は知らず知らずに汗をかくので、水分補給が大事です。でも、がぶがぶ液体を飲むと、消化器に負担がかかります。
水分を取るなら体温以上のノンカフェインを一口ずつ。なにより、食材の細胞膜に含まれている形の水分が一番おすすめ。季節の食材を、さっぱり味で 適切に食べましょう。
シジミの味噌汁や、野菜たっぷりみそ汁はミネラルも多く本当に疲れが取れます。
適宜マイルドに温める食材も取りましょう。
夏とはいえ、気温変動が大きく、外気温がそれほど高くない、風邪にあたって冷える、クーラーで冷えるなど、「冷え」対策も同時に必要です。
マイルドに温めてくれる食材も適宜とりましょう。
薬膳では、一つの性質を使ったら、逆の性質のものもプラスする、というのを覚えておくと、味的にもおいしい料理ができます。
たとえば、ゴーヤなど、冷たくしてくれる食材には、こしょう、しょうが、鷹の爪、花椒など、温める食材もプラスするなど。
湿邪をさばく食材を取りましょう
日本の夏は高温多湿。「湿邪」という、体内の余分な水分が、様々な症状を起こします。たとえば、余分な水分の代表、むくみ。さらには、疲れやすい、体が重だるいなど。
ソラマメ、枝豆などの豆類は、湿気をさばいてくれるうえ、胃腸の消化吸収能力を高め、余分な水分を排泄する という、夏にもってこいの食材。
緑豆もやしも、豆の性質を持っており、余分な水分を排出してくれます。安価なので、炒めもの、サラダ、汁や麺の具など、積極的に使いましょう。
トウモロコシは、胃腸の機能を補って夏バテを予防、改善します。ヒゲにも薬効があるので入手出来たらお茶にして飲みましょう。甘く香りが良くておいしいです。
参考文献リスト
薬膳を知りたい方へ、参考文献をご案内します。
中医学、東洋医学、薬膳、はたいへん奥が深く、歴史も長く、各流派により諸説あります。
どの本も、自分の体を観察しながら活用ください。
食品の説明は、本によってばらけています。
身につけるには、ネットで調べるのではなく お好きな本を1冊選んでお手元へ。著者の考え方が体にしみこみます。ソースがバラバラの情報より、手で触れる本のほうが、ずっと役に立ちます。
早乙女 孝子 の いつもの食材効能&レシピ帖―漢方の知恵を毎日の食卓に 食材338点レシピ151点
武鈴子著、からだに効く和の薬膳便利帳、一般社団法人家の光協会(2012)
仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006)















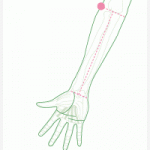



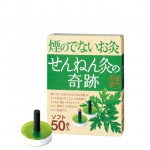





 自律神経を心地よさの中で調える
自律神経を心地よさの中で調える
 治療で心地よい瞑想状態に入る方も。
治療で心地よい瞑想状態に入る方も。